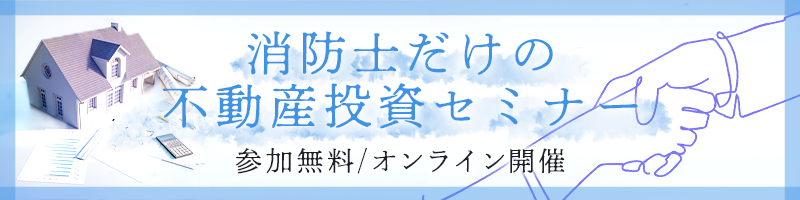消防士は地方公務員ですが、現在、地方公務員は民間の会社員と同様、老齢基礎年金と老齢厚生年金の被保険者となります。それに加えて、公務員は「年金払い退職給付」を受け取ることもできます。
この記事では、消防士が受け取れる年金額を中心に老後のお金について解説します。
消防士の老後に必要なお金
生命保険文化センター「生活保障に関する調査(令和元年度)」によると、老後の最低日常生活費は平均22.1万円/月、ゆとりある老後生活費は平均36.1万円/月となっています。老後の生活期間を65歳から90歳までの25年間とすると、それぞれ総額で6,630万円、1億830万円必要となる計算です。
人によって老後に必要な生活資金額は異なりますが、老後の生活が想定しにくい若い世代ほど、この金額を目安にライフプランを立てるといいでしょう。
※出典:生命保険文化センター「生活保障に関する調査(令和元年度)」
消防士の年金制度の変化
会社員や公務員が加入する年金は、国民年金保険と厚生年金保険の2階建てが基本となっており、保険料は給与から天引きされます。
公務員はかつて厚生年金保険とは異なる共済年金の被保険者でしたが、平成27年10月に共済年金は廃止され、厚生年金保険に一元化されました。一元化により、共済年金独自の加算であった職域年金相当部分が廃止され、「年金払い退職給付」が新たに設けられました。
年金払い退職給付は、所定の算式で求めた金額を毎月積み立て、原則、65歳から終身退職年金と有期退職年金が支給されます。終身退職年金は生きている限り、有期退職年金は一定期間(10年または20年)受け取れます。(地方職員共済組合「年金制度について(概要)」
消防士の年金はどれくらい?
消防士の場合、どのくらい年金が支給されるかシミュレーションしてみます。ここでは現在35歳の消防士(夫婦2人、専業主婦、子ども2人)が定年(65歳)まで勤めた場合を想定します。今回は、下記の「経験年数別平均給料月額」をもとに、4.5月分の特別給(賞与)を12で除した金額を加算し、年金額算出の基準となる平均給与(標準報酬月額)を44万円、勤続年数を40年として試算します。
<消防士 経験年数別平均給料月額と推定特別給(賞与)>
| 経験年数 | 平均給料月額 | 特別給 (月額換算) |
| 1年~4年 | 193,416円 | 72,531円 |
| 5年~6年 | 219,168円 | 82,188円 |
| 7年~9年 | 239,083円 | 89,656円 |
| 10年~14年 | 272,164円 | 102,062円 |
| 15年~19年 | 319,088円 | 119,658円 |
| 20年~24年 | 356,133円 | 133,550円 |
| 25年~29年 | 378,633円 | 141,987円 |
| 30年~34年 | 397,949円 | 149,231円 |
| 35年~ | 380,973円 | 142,865円 |
(総務省「平成31年地方公務員給与実態調査-第6表-」 表中の平均給料月額は一般行政職の数値)
▼公的年金から受け取れる年金額
では、公的年金からいくらの金額を受け取れるのか、試算をしてみます。なお、年金額は、将来の物価水準や賃金の水準によっても変動するため、あくまで目安と考えてください。
————————–
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、40年間の加入で満額を受給でき、年間の年金額は毎年改定されます。ここでは78万円(令和3年度の満額は78万900円)として試算します。また専業主婦である妻も老齢基礎年金を満額受け取れることとします。
78万円×2=156万円
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、給料だけでなく各種手当や特別給の額によっても変動するため、人によって差が出やすい要素です。前述の通り、標準報酬月額を44万円として算出します。なお妻には厚生年金被保険者期間がないものとします。
44万円 × 5.481/1,000 × 480月
= 115万7,587.2円
≒ 116万円
- 老齢給付として受け取れる年金額
156万円 + 116万円
= 272万円
- 25年間の総受取額
272万円 × 25年 = 6,800万円
————————–
受け取る給与や特別給の額が多いほど、支払わなければならない保険料は高くなりますが、その分、老後に受け取れる年金額も増えます。
経験年数(勤続年数)を重ねるほど、給与や特別給の額が増えますので、定年退職か自己都合退職(普通退職)かによっても受け取れる年金額は変わります。また公務員には年金払い退職給付があり、上記の試算金額に加算される点は公務員のメリットといえます。
さて冒頭に紹介した「ゆとりある老後生活費」より、老後の生活に1億円が必要である場合、公的年金だけ(試算額6,800万円)では不足していることがわかります。退職手当で約2,000万円を受け取れたとしても、個人で準備する私的年金の活用が重要となります。
そこで、税制面で優遇されているiDeCo(個人型確定拠出年金)への加入も検討してみましょう。
▼iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すれば年金を増やせる
iDeCo(個人型確定拠出年金)は任意で公的年金の上乗せ年金として活用できるものです。年金額を上乗せできるだけではなく、拠出金を全額所得控除(収入から差し引くこと)できるため、節税効果も期待できる非常にお得な制度です。
2017年から、公務員もiDeCoに加入できるようになりました。ただし毎月拠出できる金額に上限があり、公務員は月額1万2,000円(年額14万4,000円)までとなっています。
投資先は自分で選べますが、受け取れる年金額は運用成果により変化します。リスクを取るほど受け取れる年金額が増える可能性がある一方、期待したほどの金額を受け取れないこともあります。iDeCoは投資経験や知識に見合う投資先を選べ、税制優遇を受けながら中長期的に運用益を目指すための制度です。
ここでは楽天証券のシミュレーションツールを使用し、「運用益は求めつつ、安全な運用を目指す」場合(運用利回り3%)、「リスクを取り、積極的な運用を目指す」場合(運用利回り5%)で試算します。毎月1万2,000円、25年間(35歳から60歳)まで運用した合計額は次の通りです。
| 運用利回り3% | 運用利回り5% | |
| 積立元金 | 360万円 | 360万円 |
| 合計額 | 535万2,094円 | 714万6,117円 |
| 運用益 | 175万2,094円 | 354万6,117円 |
(楽天証券のシミュレーションによる試算。年収450万円の場合の節税額72万円(25年間)を含みます)
運用利回り5%の運用益はほぼ積立元金と同額で、結果700万円ほどの年金を準備できています。運用益は不確定ですが、iDeCoを活用することで、目標となる1億円に近付けることができます。
公的年金だけでは十分な老後の生活資金を得られない
iDeCoを活用して初めて、ゆとりある老後の目標額に近付きましたが、それでもなお不足しています。必要資金額や年金額は人によって異なり、若い人ほど老後の生活状況は想像しにくく、準備は遅れがちです。しかし資産運用は早めに始めるほどリスクを軽減することができますので、この機会に老後の生活について考えてみてはいかがでしょうか。